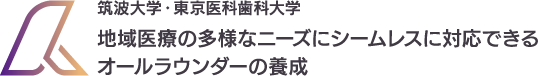都立駒込病院 緩和ケア科 長岡広香先生が筑波大学医学群医学類4年生向けに「看取り」をテーマに講義してくださいました!
7月7日(月)、筑波大学医学群医学類の4年生を対象に行われた「緩和ケア」の講義に、都立駒込病院 緩和ケア科の長岡広香先生をお迎えしました。
今回の講義では、「看取り」をテーマに、終末期を迎えた患者さんやそのご家族に対して、医療者がどのように寄り添い、関わっていくべきかを教えていただきました。
まずはじめに、命の終わりが近づいたときに見られる体の変化(呼吸や皮膚の変化、意識の低下など)について説明がありました。
こうした変化に対して、医師や医療スタッフは事前に備えておき、状況に応じて柔軟に対応することの大切さが強調されました。
また、「もし自分の家族が看取りの時期を迎えたら、どんなことが気になるか」という問いかけがあり、学生それぞれが自分の立場で看取りを考える時間も設けられました。
患者さん自身にも、たくさんの気がかりがあります。
たとえば、「痛みがつらくないか」「自分の希望通りの治療が受けられるのか」「家族に迷惑をかけていないか」「死への恐れ」「やり残したことはないか」といった思いです。
こうした患者さんやご家族と向き合う際に大切な考え方として、「DoingではなくBeingであること」が紹介されました。
これは、「何かをしてあげる」こと以上に、「そばにいて、思いに寄り添う」ことの大切さを表した言葉です。
ひとりひとりの人生の終わりを、日常の延長ではなく、大切な時間として丁寧に向き合う姿勢が求められること、そのためには終末期になる以前から、コミュニケーションを通して関係性を築いていくことが大切であることを学びました。
講義の後半では、がんを患った男性が、診断を受けてから最期を迎えるまでの様子を家族が記録した「エンディングノート」という題名の約1時間のドキュメンタリー映像が上映されました。
病と向き合う姿、ご家族の支え、穏やかな旅立ちの瞬間が映し出され、学生一人ひとりが「看取り」について深く考え、感じる貴重な時間となりました。