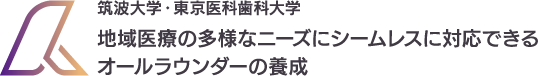筑波大学附属病院総合診療科実習の紹介
筑波大学では5年次~6年次を対象に1か月間の総合診療科クリニカルクラークシップ/医療概論Vを組み合わせた実習をしています。この実習では1か月間のうち3週間は、先日ご紹介した水戸地域医療実習水戸地域医療実習(5年次)レポート(筑波大学) | ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業のように、茨城県内の地域で1~2週間ずつ2~3か所の滞在型実習を行い、残りの1週間は筑波大学附属病院で総合診療科の実習を行います。
今回は筑波大学附属病院での1週間の総合診療科の実習を紹介します。筑波大学附属病院総合診療科では入院患者を受け持っていないため、学生は外来での実習とワークがメインになります。
学生は4~5人1班で回りますが、午前中は各々が筑波大学附属病院や近隣の筑波メディカルセンター病院等に分かれて初診患者の予診をとります。筑波大学附属病院ではビデオ撮影の許可を頂いた患者さんには学生問診の様子のビデオも撮影させていただきます。
午後は大学に集まり、以下のような実習を行っています。
①ケースレビュー
午前中に筑波メディカルセンターで予診をとった症例について、担当した学生が現病歴をプレゼンテーションし、指導医がファシリテートしながら学生同士で質問や議論をして鑑別診断、アセスメントやプランを検討していく臨床推論に関する実習です。毎日1~2症例を1時間かけて行っています。

②ビデオレビュー
午前中に筑波大学附属病院の初診を受診され、ビデオ撮影の許可を頂いた患者さんへの問診の様子を指導医と学生で供覧し、観察者の学生や指導医からフィードバックをうける実習です。問診の内容というよりはコミュニケーションに着目して観察しています。

③SP(模擬患者)コミュニケーション実習
つくばSP会のSPさんに協力を頂いて、学生が問診を行い、その後アセスメントやプランも含めて指導医にプレゼンテーションをするという実習です。2時間かけて3症例行いますが、それぞれ違う患者をSPさんが演じ分けてくださっています。コミュニケーションに気を付けるだけでなく、鑑別診断を考えながら問診するという点では学生にとってはやや高度な内容となっています。観察者の他の学生、SPさんや指導医からコミュニケーションや問診内容、臨床推論に関してフィードバックを行っています。
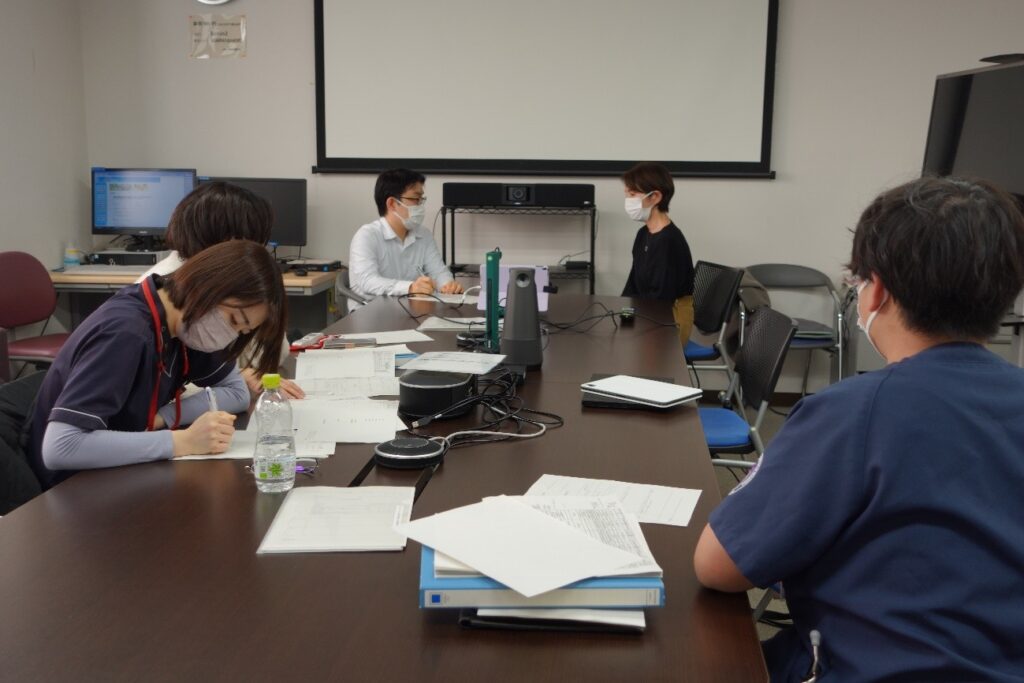
④症例カンファレンス
1週間の最後の金曜日には、その週大学病院の総合診療科を受診された全症例を教授、指導医、レジデント、学生を含めて全員で振り返ります。学生が担当した症例には学生にショートプレゼンを担当してもらっています。

その他にも、身体診察から鑑別疾患を考える実習、クリニカルインディケーター(感度/特異度、尤度比、NNT等)を計算するワーク、EBMに関する演習(1週間かけて各学生が経験症例をもとに臨床疑問を考え、EBMのステップに沿ってワークを行い発表する演習)も行っています。また、毎朝、症候学などに関する指導医からの30分間のミニレクチャーも行っています。さらに、1週間の間に緩和ケア科での半日間の実習、漢方外来での実習もあり、盛りだくさんな内容となっています。
実習後の学生アンケートでは「臨床推論の基本的なプロセスについて理解が深まったか」という質問に対しては47.9%がとてもそう思う、52.1%がそう思うと回答しました。
以下は自由記載の内容の一部抜粋です。
・問診を中心に、診断を考える上で重要なテクニックについて学び、現在の自分に不足している点や反対に達しているであろう点について客観的な意見を頂けた貴重な機会だった。
・鑑別診断をじっくりと考える経験ができた。緩和ケアや漢方といったあまり他の診療科で扱わない内容に触れることができた
・臨床推論、EBM、問診、緩和ケアなど様々な経験を積むことができた。特に、自分で問診をとって、その症例の臨床推論について考える過程はとても勉強になった。
・臨床推論とコミュニケーションをとる機会が多かった点が良かった。
・自分が問診している様子をビデオに録画して、振り返ることで、客観的に自分の良い点と悪い点を見つけることができ て、とても良かったと思う。
・EBMの演習が今後研修医になってからも活かせる勉強になったと思う。