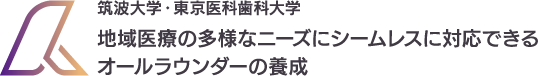水戸地域医療実習(5年次)レポート(筑波大学)
筑波大学では5年次~6年次を対象に1か月間の総合診療科クリニカルクラークシップ/医療概論Vを組み合わせた実習をしています。この実習では1か月間のうち3週間は、茨城県内の地域で1~2週間ずつ2~3か所の滞在型実習を行い、残りの1週間は筑波大学附属病院で総合診療科の実習を行います。今回は地域の滞在型実習の一つである、水戸地域医療実習(1週間)についてご紹介します。
水戸市保健所と連携し水戸市内の地域医療を担う医療・福祉・保健・介護の様々な分野で実習を行い、地域診断のグループワークを通して、水戸市ならではの暮らしを支える医療の在り方について考える実習内容となっています。
<実習目標>
この実習は、普段、大学病院中心の実習をしている医学生の皆さんに、水戸市内の地域医療を担う様々な分野について現場で実習を行うことを通して、地域包括ケアシステム、多職種連携や健康の社会的決定要因について理解を深めることを目的としています。また、「住人水戸色(じゅうにん みといろ)」をコンセプトとして、地域診断のグループワーク、レポート作成を行っています。見学だけではなく、様々な場で地域住民や医療介護職員と意見交換する実習を通して、「十人十色」である住民の暮らしを知り、水戸市ならではの特色「水戸色」を見つけてもらうことで、水戸市の地域医療の実態を知り、地域において医療従事者として果たすべき責務について考える機会を提供しています。

<スケジュール例>
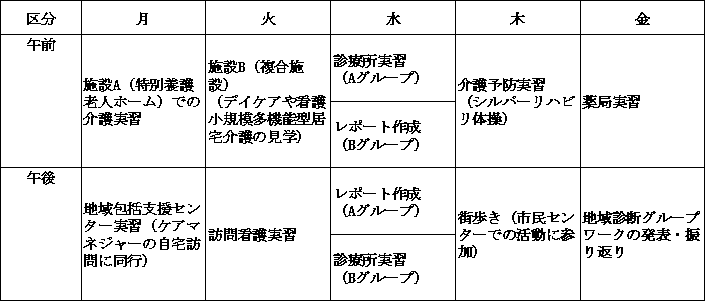
実習協力施設(2024年度):水戸病院、クリニック健康の杜、廣瀬クリニック、在宅緩和ケア もみのき診療所、訪問ステーション みかん、フロイデ水戸メディカルプラザ、ツクイ・サンフォレスト水戸、ユーアイの家、特別養護老人ホーム もくせい、グリーンハウスみと、水戸市総合福祉作業施設(はげみ、のぞみ)、アルファーム薬局渡里店、フローラ薬局河和田店等
<地域診断>
地域診断とは、地域地域について客観的指標やきめ細かい観察を通して、地域の特徴を把握し、地域の健康課題について分析すること1) 。情報収集、仮説作成、街歩き、地域アセスメント、アクションプランの5つのステップに沿って行うことです。
地域診断を行うため、1週間のスケジュールの中に、「街歩き」という時間を半日設定し、街を歩いて歴史的背景についての理解を深めたり、住民へのインタビューを行うなど、地域診断の一環として行うフィールドワークを取り入れていれ、調べたことをグループでレポートにまとめてます。
実際に作成された地域診断レポートでは、「高齢者の孤立が課題であり、若年者との交流を増やすために、市民センターのイベントを水戸市の小中高と合同で開催する」「認知症を早期発見・早期介入するため、町内会のリーダーや地域包括支援センターなどが地区ごとに連携する」
「介護保険の対象外となった方への支援として、高齢者が隠れたスキルを活かすことができる『教える』場を提供する」などの内容がありました。このように地域の健康課題に向けた具体的な提言も認められ、保健所の職員と意見交換を行いました。
<実習の風景>




<実習の感想(抜粋)>
・介護施設を複数個所見ることで施設の役割について、実際に目で見て理解することができた。その人らしいケアができるよう施設の職員が工夫をしており、病院との違いを感じた。
・患者さんやケアマネジャーが参加するサロンでは、医療や介護に期待することをいろいろな目線で学ぶことができた。介護をしているご家族や利用者さんの生の声を聴くことで退院後の生活について知ることができた。
・デイケアやフィットネス、カフェ、有料老人ホームなどが併設された複合施設では健康な時から関わることで、その場所に親しみやすくなるメリットがあると感じた。
・地域のクリニックは、検査や治療だけでなく、生活や家族の悩みなどの相談もできる身近な存在であることを知った。