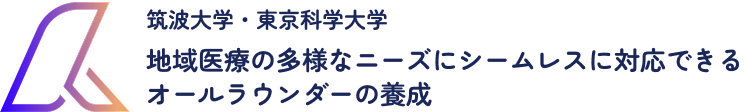- 東京科学大学
- 活動報告
令和7年度 医学導入講義・実習で、360度VR教材を用いた医療現場の体験を行いました (東京科学大学)
東京科学大学では1年次を対象に、医学導入講義・実習を行なっています。
この講義はこれから医師となるため成長していく1年次の学生が、講義・グループ討論・医療現場での早期実習などを通して、医療・医学の現場、医療者及び医学者となるための資質と能力(コンピテンシー)、将来のキャリアの展望、グローバルコミュニケーションについて理解を深めるとともに、医療現場・研究現場・イノベーションと体験することを目的としています。
今回は、2025年9月16日(火曜日)に、360度VR教材を用いた在宅医療現場の体験と、医療現場のコミュニケーションに関するグループワークを行いました。
360度VR教材を用いた医学導入講義は、今回が3回目になります。
在宅医療現場のVR体験では、嚥下機能の低下した患者さんの自宅を訪問し、医師・歯科医師・看護師と患者さん・ご家族がどのようにコミュニケーションを取り、診察や嚥下機能の確認を行い、今後のケアを考えていくのかという場面を視聴し、考察を行いました。
コミュニケーション入門の実習では、患者さんと医師の間の良くないコミュニケーションの事例に関する360度VR教材を視聴し、問題点についてグループでディスカッションを行い、学生役・患者役などに分かれてロールプレイを行いました。
<実習の感想(抜粋)>
在宅医療現場体験:
医学に関する基礎知識・基礎的な姿勢を座学形式で学ぶものだと思い込んでいたが、VR ゴーグルを用いて行う自宅診療の見学はとても臨場感があって、自分が何を観察すべきなのかの基礎が理解できたと思う。
VR ゴーグルを用いた映像の確認問題を解く前後に,1回ずつ映像を見る機会があったことで,1回目と2回目で視点を異にして見ることができた。
VR で実際に見学することが難しい訪問治療の流れを体験できたのが興味深かった。ただ患者さんを見るのではなく、その部屋や介護者の表情などを観察して情報を集め、判断材料にしていくということを知った。
医療コミュニケーション入門:
今まで本格的に習ったことのない分野だったのがとても興味深かった。 ロールプレイは難しかったが、基準を自分たちで考えたことによって、より意識することができた。
医療の場において、どのように患者と適切なコミュニケーションとは何かを例を通して考えることで、自分の立場になってどのようにコミュニケーションをとっていけば良いかを考えることが出来てよかった。
VR を用いて動画を見ることで、コミュニケーションが良いときと悪い時の現場の雰囲気を肌で感じれたので良かった。また、ロールプレイングをしたことで、患者さんとのシャドーイング実習に向けて良い準備ができた。
また、VRゴーグルの操作性や、以前の授業と同様にVR酔いに関する意見も寄せられました。
<実習の様子>