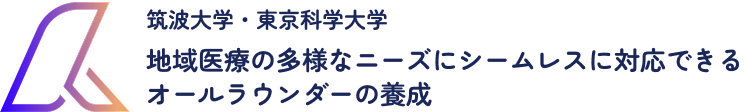実践とリサーチを往還する意義
学会発表を通じて得た学び
筑波大学地域医療教育学では、学生たちが継続的に地域に入り、そこに暮らす人々や医療者と密に関わりながら地域医療の現状や課題を学ぶと同時に、体験から得た気づきや疑問を自身のテーマとして医学研究に取り組む研究室演習を行っています。
今回は、その成果の一つ、第16回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会での発表について、学生同士で振り返りをしてもらいました。

|
座談会実施日
|
2025年6月30日 |
|---|---|
|
参加者
|
山本 司(6年)、中川 佑里子(4年)、佐藤 礼優(2年) |
|
同席者
|
近藤 真樹、地場 凜々子(以上、5年)、海野 彩花、本山 岳志、竹尾 七空、中西 優奈(以上、4年)、金子拓生(1年) 後藤 亮平 准教授、前野 貴美 講師、孫 瑜 特任助教、橋本 恵太郎 特任助教 |
※記事は座談会の一部を抜粋し、再構成しています。
第16回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会への参加について
開催期間 |
2025年6月20~22日 |
|---|---|
開催地 |
札幌市 |
演題数 |
口演発表5、ポスター発表3、
※研究室演習での発表数。筑波大学全体では計9演題を発表 |


地域活動を起点にした研究発表で
二重の学びが実現
――では学会発表について、互いに質問しあいながら振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。
佐藤
2年の佐藤です。今回私は、「地域医療の現場を体感して知る実際」と題し、昨年11月に行われた常陸太田市での地域医療合宿についてポスター発表をさせてもらいました。
昨年、1年生の9月という何も知らない状況で地域医療合宿を体験し、地域で活動されている医師の姿を見ていろいろなことを学んだのですが、その時には体験で得たものをなかなか言語化できなかったんですね。それを今回、活動報告としてまとめるにあたって担当の橋本先生とコミュニケーションをとっていくことで、自分の体験したことをしっかり言語化することができました。また、活動体験のロジックを教えていただいたことで目的や狙いがわかり、自分の活動を振り返ってもう一度学びの機会を得られました。それらの点で、今回の学会活動には意義があったと思っています。
考察のプロセスにおいては、高学年の学生の体験についてもアンケートを通じて知ることができましたし、ひたち太田家庭医療診療所の大森先生のプロフェッショナリズムが表れているエピソード――例えば、目が見えない患者さんも大森先生のことは見えている、みたいなお話をいくつかお聞きすることもできました。自分がなぜ地域に根差した医師を目指したのかみたいな根幹的なことも学会が近づくにつれてあらためて考えましたし、本当にいろいろな角度から学びがあったと思います。

初めての学会で感じた
圧倒的な熱量!
佐藤
まず、プライマリ・ケアの領域でこんなに多くの種類の研究がなされているんだなと驚きました。そしてそこに関心を持っている学生がこんなに多いんだと圧倒されましたね。
私はまだ全然知らないことの方が多いので、次の活動や研究につなげられるような学びを得たいと思って今回学会に参加しましたが、自分のやりたいと思っている終末期ケアや死生学の口演を見たりすることで学びを深めることができました。また、高校生に対する医療体験など、次世代に地域医療をつないでいく活動にも興味が湧きました。
佐藤
私がずっとかかっていた医師の先生が、患者さん一人ひとりに向き合いそのすべてを診るというような方で、そういう医師になりたいという思いが高校生の頃からありました。それが常陸太田の合宿で、へき地でも医療資源が乏しくてもその地域の人たちのために最善を尽くすという大森先生の姿を見たことで、また新しい理想の医師像を得ることができました。
学会が終わった今も、医療概論で大森先生の活動や背景にある地域課題などについて考える機会があり、合宿の時からずっと学びが続いていると感じています。

夢中になって研究に取り組む
中川
4年の中川です。私は2回目の学会参加で、今回初めて口演発表を行いました。
初めての発表、しかも質的研究だったのでひたすら手探りで、担当の後藤先生にも本当に何回も繰り返し見ていただきました。演題は「プライマリ・ケア医が行うプレコンセプションケア外来で受診患者はどのような経験をしているのか?」です。
発表後の感想としては、とにかく“こんなに研究って愛着が湧くんだ!”という気持ちです(笑)。
――わかる気がする(笑)。
中川
全部のスライドに気持ちがこもっていて、それだけ納得がいくものに仕上げることができてすごくよかったなと思う一方で、体調のせいで声が出ず、伝えきれなかったことに悔しい気持ちもありました。プレコンセプションケアはこども家庭庁が性と健康に関する正しい知識の普及と相談支援の充実に向けて5か年計画を発表したばかりだったので、そんなホットな話題だということも質問が来たらしゃべろうと思っていたのに、質問が来なかったり(笑)。
振り返りとしては、リサーチクエスチョンの段階からもっと伝えたいことにつなげていけるように設定できればよかったのかなと考えたりしています。そういう点を次に活かしていけたらと思います。

概念的だった理解が、
臨床的視点での理解に
中川
「ネガキャン・コレクション2025 ~それは事実と違います!~」や「家庭医だからこそできるウィメンズヘルス」というセッションでは、実際に診療されている先生方の意見として総合診療ができることやその強みを聞くことができ、すごく刺激になりました。
また、メンタルヘルス系の「Difficult Patient への対応・医療者自身のケア ~トラウマインフォームドケアの視点~」というセッションでは、授業で概念的に学んだものを実際の診療でどうアプローチするのか聞けたことが、今後Clinical Clerkshipに行くにあたってとても勉強になりました。
私がなりたい医師像は、関わりの中で人の心をほぐしていけるような医師、患者さんが困っていることに対してその解決を手伝っていけるような医師です。今回そういう話をたくさん聞けたことがよかったと思います。
中川
研究はまだあまり考えられていないのですが、プライマリ・ケアでのプレコンセプションケア外来について調べるのもいいなと思っています。あと、今回の学会で出会った「逆境的小児体験(Adverse Childhood Experiences: ACEs)」というテーマ、これは小児の時に大きなトラウマとなりうるような経験をした人は将来メンタル系の病気やがん、生活習慣病などのリスクが上がるというもので、すごく興味を持ったので、これも調べてやってみたいなと思っています。

地域活動で関わった人たち
みんなの思いを背負って発表
山本
6年の山本です。自分は今年が2回目の学会参加でしたが、発表は今年が初めてで、大きな挑戦の年となりました。口演発表とポスター発表、2つの発表をさせていただきました。
口演発表の演題は「うつ病患者への偏見やうつ病の認識に関する実態調査」です。このテーマは医学的にすごく意義があるというよりは、こういう研究テーマが大事だろうと考え選んだものです。実際、終了後にたくさんの学生が声をかけにきてくれて、うつ病の研究に関心をもってもらえたと感じることができ、発表をしてよかったと思いました。
また、今回は量的研究でしたが、量的研究は型が決まっていてどうやって進めたらいいのかよくわかるし、先生からのフィードバックもたくさんもらえたので、初めて取り組む研究としてはすごくやりやすかったです。
ポスター発表の方は、「一つの地域に継続的に関わることの意義」と題し、2年ほど前から続けてきた茨城県神栖市での活動について、“学生が地域活動を継続することの意味ってなんだろう?”ということをまとめました。実は口演の方はあまり緊張しなかったのですが、ポスター発表の方はめちゃくちゃ緊張しました(笑)。
山本
いや、自分でも久々に緊張していて、なんでこんなに緊張するんだろうって考えた時に、このポスターには自分一人の思いだけじゃなく、今まで参加してくれた学生や神栖の住民の方の思いがグッと詰まっている、これを上手く伝えたいという思いがあったからだと気づいたんですね。でも緊張してうまく伝えきれなかったので、今後はもっと自分の思いを相手に届けられるような話し方や発表を考えていきたいなと思っているところです。

学会でさらに広がる
知識と人のネットワーク
山本
自分が関心を持ってやっている神栖の活動や研究のことを伝えたいというのが一つ、あとは有名な先生方やまだ知らない学生と話して、さらに交流を深めていきたいというのが一つ、大きくその二つかなと思います。
山本
昨年11月の第3回日本地域医療学会で仲良くなった長崎大学の学生が今回も来ていました。ポスター発表の会場でいろいろ話をしていると、「私も地域活動をやってみたい」という話になり、長崎大学の先生も一緒になって、神栖のよさや、なぜこんなに継続して関わることができているのかという話をすることができました。それがかなり嬉しかったですね。

学会は一つの通過点
目指す医療に向けて、学びは続く!
――地域活動から学会活動への一連の学びを通じて、将来医師として地域を診ていく視点は得られたと思いますか?
佐藤
私は2年で医師になるのはまだ先なので、あまり解像度が高くないのですが、今後への足掛かりとして一つ気づいたのは「コミュニケーションの重要性」です。今回私が報告した大森先生の医療を見ても、一人ひとりの患者さんとの対話を重視されていて、それによって癒しが与えられているように思います。そこに、医療を人がやっている意義があると感じました。また、学会の死生学に関するシンポジウムでは、医師の態度によっては7割のコミュニケーションが有害になってしまうという話も聞きました。
コミュニケーションの重要性について今後も考え続け、それを足掛かりとして自分が目指す医師としてのビジョンを確立していければいいなと思っています。
中川
私は今回の活動を通じて、医師の研究は単なるデータの集積ではなく、これまで関わってきた患者さんや地域の方々の思いや体験を形にする行為だと実感しました。
私が取り組んだのは、患者さんの生の声のインタビュー音声を分析する質的研究でしたが、その中で、妊娠に至るまでの医学的な介入だけでなく、その人の生活背景や日々の思いが健康と深く結びついていることに強く気づかされました。
こうした視点を培えたことで、将来医師として、予防や生活支援も含めて「地域全体を診ていく」姿勢を持つことにつながったと感じています。
山本
自分は来年から臨床の現場に出ていきます。最初に佐藤くんが話してくれた振り返りとも近いのですが、初めはなんとなく漠然と「地域をやりたい」とか「人の役に立つ仕事をしたい」というところから入って、地域活動などをやりながら学年が上がり、今回学会に参加したことで自分がやりたいと思っていたことはちゃんと社会ニーズがあるんだということを再確認することができました。また、同じように地域医療を目指している学生がこんなにいるんだということが、すごく安心感にもなりました。
地域医療は幅広く、その中で自分がどこに興味を持っていのるかも学会に参加するとわかります。こうした経験が、自分の強みになると感じています。
――皆さん、今日は本当にありがとうございました!